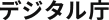資本主義 資本主義 概念[表示] 経済体制[表示] 経済理論[表示] ...
...
資本主義
| 資本主義 |
|---|
| 経済体系 |
|---|
資本主義(しほんしゅぎ、英: capitalism)または資本制は、生産手段の私的所有および経済的な利潤追求行為を基礎とした経済体系である[1][2][3]。資本主義を特徴づける中心的概念には、私的所有、資本蓄積、賃金労働、自発的交換、価格体系、競争市場などがある[4][5]。資本主義の市場経済では、投資の意思決定は金融市場や資本市場の中で所有者によって判断され、生産物の価格や配分は主に市場での競争によって決定される[6][7]。
資本主義の形態は、経済学者・政治学者・歴史学者などにより、レッセフェールまたは自由市場による資本主義、福祉資本主義、国家資本主義などの多数の議論がある。これらの経済体制では、自由市場や自由競争と、公権力(社会政策による政府規制などの経済的干渉主義)との間のバランスが異なる[8][9]。現在の資本主義経済の大多数は、自由市場と政府による干渉の要素を結合した混合経済で、経済計画を持つ場合もある[10]。
資本主義の弊害に対し、修正や反対をする概念や立場には修正資本主義、反資本主義、社会主義、共産主義、第三の道、第三の位置などがある。また自由競争を更に推進する概念や立場には新自由主義、リバタリアニズムなどがある。
目次
用語
「資本」(英語: capital)の語源は、ラテン語で「頭」の意味を持つ「caput」で、12世紀から13世紀にかけて動産を意味するようになり、更に「資本家」や「資本主義」との言葉が派生した[11][12][13]。「資本家」(英語: capitalist)との用語は、17世紀に「資本の所有者」との意味で使用されるようになった[14]。
「資本主義」(英語: capitalism)との用語は、1850年にフランスの社会主義者ルイ・ブランによって現代の意味で使用され、「私が資本主義と呼ぶものは、ある者が他者を締め出す事による、資本の占有である」と記した。また1861年にピエール・ジョゼフ・プルードンは「資本主義の経済社会体制では、資本は労働する者には所属しない」と記した[15]。1867年より発行されたカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによる著書『資本論』での用語「資本家(資本制)システム」(英語: capitalistic system)および「資本家(資本制)生産様式」(ドイツ語: kapitalistische Produktionsweise、英語: capitalist mode of production)も、日本語訳では「資本主義」とされた場合が多い[16]。
「資本主義」の同義語または類義語には、以下がある。
- 経済的自由主義 (Economic liberalism)[17] – 自由主義の用語
- レッセフェール[18](自由放任主義) – 古典的自由主義
- 資本制生産様式(Capitalist mode of production) [19] - マルクス経済学の用語。詳細は上記参照。
- 市場自由主義(Market liberalism) [20]
「資本主義」の用語は経済体制(生産のための組織が資本により作られている経済体制)を指すもので、主義・主張・思想を指すものではない。この経済体制を肯定する立場からは、通常は「自由主義」や「自由経済」などの用語が使用されている[16]。
概要
資本主義は、自由市場での交換による金銭的利益の個人的蓄積という欲望によって推進される「交換のための生産」(利益のための生産)である。資本家による生産は「使用のための生産」では無いが、市場は消費者と社会全体のニーズと要望によって推進される。現代の主流の経済学、特に経済的な右派は、自由市場を通じた「見えざる手」が、社会的生産をこれらのニーズと要望に合わせる事ができると主張している.[21]。
一般的には、経済システムまたは生産様式としての資本主義は、以下のように要約できる[22]
- 資本蓄積[23]:利益と集積のための生産。生産の全部または大多数を占め、従来は共同体や家庭などで行われた日用品生産の縮小や廃止をもたらす。使用価値に代わり、交換価値の最大化を目指す[21]。
- 生産手段の私的所有[9](私有財産制)
- 賃金労働[24](労働市場を介した労働)
- 利潤追求のための投資[25]
- 競争的市場における資源確保のための価格決定メカニズム[9]
基本原理としては生産手段を持つ資本家が、生産手段を持たない賃金労働者を使用して利潤を追求する社会システムである[26]。
歴史
近代以前
近代以前より、多くの時代・地域で資本は小規模に存在していた。現代的な形の資本主義は、ルネッサンスにおける農業資本主義と商業主義の出現にまで遡ることができる[27]。また私有財産制は古代のアテナイや古代ローマにも存在した。
産業革命と初期資本主義
18世紀半ば イギリスより産業革命が発生し、デイヴィッド・ヒュームとアダム・スミスらの新しい経済理論家グループは、従来の重商主義に異議を唱え、市場経済では自己利益のための投資が「見えざる手」により全体の効率と成長に導かれる、とした(古典派経済学)。他方で手工業生産の衰退や囲い込みなどにより、伝統的な共同体が崩壊し、都市労働者が増大して労働者階級(プロレタリアート)が形成され、劣悪な労働条件や低賃金が拡大した。このためシャルル・フーリエらは社会改革を提唱した(空想的社会主義)。
1780年代からのフランス革命などの市民革命(ブルジョワ革命)では、私有財産制が確立して経済的自由主義が拡大した一方、経済的平等を重視する立場から社会主義が登場した。1867年、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスらは『資本論』で、資本主義の拡大により国家の役割は縮小するが、資本主義の本質は資本家による労働者からの搾取であり、資本家は富を蓄積し労働者は貧困を蓄積するため、必然的に革命が発生して、資本主義社会(生産手段の私的所有)から社会主義社会(生産手段の社会的所有)に移行する、とした(マルクス経済学)。
18世紀後半のアメリカ合衆国独立以降、ロックフェラー、モルガン、メロンの三大財閥が市場を独占し、自由競争を妨げているとして独占禁止法(反トラスト法)が制定され、法廷闘争が行われた。なお日本の明治維新は半封建的な資本主義との議論がある(日本資本主義論争)。
第一次世界大戦後の世界恐慌と修正資本主義
1914年に第一次世界大戦、1917年にロシア革命が発生して社会主義国が誕生し、産業の公有化や計画経済を行った。1917年 ウラジーミル・レーニンは『帝国主義論』で、現在の資本主義は独占資本主義に転化し、植民地搾取により延命する帝国主義である、とした。各国の社会主義運動は分裂し、資本主義の枠内での社会改良を目指す者は「社会民主主義」、レーニン流の革命を目指す者は「共産主義」と呼ばれるようになった。
1929年、世界恐慌により大量の失業者が発生して社会不安が増大し、従来の資本主義理論(レッセフェール、景気循環理論)への懐疑が広がった。アメリカ合衆国はケインズ経済学の有効需要理論を採用しニューディール政策を実施した(修正資本主義)。イギリスやフランスはブロック経済政策により自由貿易を制限した。広大な植民地を持たない諸国では、イタリアのファシズムは第三の位置としてコーポラティズムによる経済を提唱し、ドイツのナチズムは大規模な雇用創出を行って生存圏を主張し、日本では統制派により統制経済や大陸進出が進められた(集産主義、軍事ケインズ主義、国家総動員体制)。
第二次世界大戦後
冷戦の発生により、アメリカ合衆国や西ヨーロッパは「西側、自由主義(資本主義)陣営」、ソビエト連邦や東ヨーロッパなどは「東側、社会主義(共産主義)陣営」などと呼ばれ、体制競争が行われた。特にヨーロッパの資本主義諸国では労働条件の改善や労働組合の重視、社会保障などの富の再分配、主要産業の国営化などが進められ、混合経済化が進んだ(社会的市場経済、福祉国家論)。また第二次世界大戦を引き起こした経済対立の原因にブロック経済があったとの反省により、GATTやWTO協定などの世界自由貿易が推進された。アメリカでは大量生産・大量消費の経済が拡大した(フォーディズム)。社会主義国では、西側諸国による経済封鎖や軍事費負担、技術革新の遅れ、官僚主義による非効率などもあり、1991年 ソ連崩壊が発生し、中国では改革開放、ベトナムではドイモイ政策が進められた(社会主義市場経済)。
1970年以降、ミルトン・フリードマンらはケインズ主義を批判し、市場原理の拡大を提唱した(新古典派経済学、マネタリズム、新自由主義)。チリではチリの奇跡、イギリスではサッチャリズム、アメリカではレーガノミクス、日本では小泉改革などの規制緩和、民営化などが進められた。グローバリゼーション拡大により、各国政府の権限や多国籍企業への規制の縮小による雇用や安全への脅威や、格差社会の拡大も主張された(反グローバリズム)。また1990年代のインターネット普及後は、IT革命による経済効率化や情報格差も主張された。
2013年、トマ・ピケティは著書『21世紀の資本』で、長期的には資本収益率は経済成長率より大きく、富は蓄積され格差は拡大するため、格差是正には世界的な政治的再配分が必要とした。
類型
資本主義の類型には、時代・立場・観点などにより、以下などが主張されている。
- 自由放任資本主義(初期資本主義。小さな政府、夜警国家などとも呼ばれる。古典派経済学や、新古典派経済学、いわゆる新自由主義や市場原理主義などが支持する。)
- 修正資本主義(社会的公正を重視し、修正・改良した資本主義。社会改良主義、社会民主主義、民主社会主義などが支持する。福祉資本主義、混合経済、大きな政府などとも呼ばれる。)
- 独占資本主義(レーニン主義による用語。金融資本主義、国家独占資本主義、帝国主義とも。なお、この概念を受け入れない社会主義者の用語には晩期資本主義がある。)
- 国家資本主義(国家が介入または推進する資本主義。ネップ、開発独裁、日本型社会主義、社会主義市場経済などを指す場合もある。)
- 超資本主義(ベニート・ムッソリーニによる概念。第三の位置。)
- 無政府資本主義(アナキズム、および右派リバタリアニズムが提唱する資本主義。政府や国家の廃止を提唱する。)
- グローバル資本主義(グローバル化した世界における資本主義)
- 情報資本主義(情報を資本の重要要素とする資本主義)
学派
資本主義に関する経済理論や学派には以下がある。ただし多くの学派名は他称であり、その分類にも議論がある。
古典派経済学
詳細は「古典派経済学」を参照
18世紀後半以降、アダム・スミス、トマス・ロバート・マルサス、デヴィッド・リカードなどのイギリスの経済学者に代表される。従来の重商主義を批判し、労働価値説を提唱した。また重農主義によるレッセフェール(自由放任)の概念を使用し、個人の利己的な経済活動が、自由市場の「見えざる手」(需要と供給による価格決定メカニズム)によって、全体として資源の最適配分となるとした。なおジョン・スチュアート・ミルは功利主義に基づく自由主義を重視する一方、貧富の差や植民地の増大を懸念し、政府の再分配機能も重視して後の社会民主主義などの改良主義に影響を与えた。
マルクス経済学
詳細は「マルクス経済学」を参照
19世紀後半以降、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスらは、古典派経済学の労働価値説を批判的に継承して剰余価値説を提唱し、資本主義の本質は資本家による労働者の搾取とした。また資本主義は普遍的なものではなく歴史的なものであり、資本主義の矛盾が累積すると最終的には革命が発生し、社会主義社会(生産手段の社会的共有)に移行するとした。ルドルフ・ヒルファーディングは金融資本論を提唱し、ウラジーミル・レーニンは帝国主義論を提唱して帝国主義は資本主義の最終段階であり植民地主義により延命しているとした。
オーストリア学派
詳細は「オーストリア学派」を参照
19世紀後半以降、カール・メンガーらは、古典派経済学の労働価値説や生産費説に対し、功利主義による限界効用理論に基づいて消費財の価格を説明した(限界革命)。またフリードリヒ・ハイエクは経験論を重視した自由主義を唱え、理性主義や合理主義を批判し、それらに基づく計画経済(社会主義、ファシズム、全体主義)を批判した。
新古典派経済学
詳細は「新古典派経済学」を参照
19世紀後半以降、新古典派経済学(ネオクラシカル)は、アルフレッド・マーシャルなど古典派経済学の伝統を重視する限界効用理論以降の学派であり、市場経済を重視するが、市場の失敗への対応など政府の役割も認める。なお1970年代以降の新しい古典派(ニュー・クラシカル)は、ネオクラシカルの枠組みに、ミクロ的基礎づけを重視する。
アメリカ学派
詳細は「アメリカ学派 (経済学)」を参照
19世紀後半から20世紀前半のアレクサンダー・ハミルトンらのアメリカ合衆国のマクロ経済学的政策。製造業を支援するために保護貿易主義を提唱し、交通機関などインフラ建設を政府が投資し、国営銀行が投資や投機よりも商業や経済の成長を促進した。
ケインズ経済学
詳細は「ケインズ経済学」を参照
20世紀前半、ジョン・メイナード・ケインズらは、古典派経済学のセイの法則(供給はそれ自らの需要を生み出す)や古典派の公準(賃金変動により雇用調整される)を中心とした自由放任経済を批判し、有効需要理論により政府が需要創出を行い経済を拡大する事により、実在している非自発的失業を無くせると提唱して、ニューディール政策に大きな影響を与えた。
シカゴ学派
詳細は「シカゴ学派 (経済学)」を参照
1920年代以降、シカゴ学派はミクロ経済学的な手法を多種多様な分野に適用した。オスカル・ランゲは世界恐慌後、市場経済を社会主義に導入した市場社会主義を提唱した。ミルトン・フリードマンらは実証主義を重視し、ケインズ主義の有効需要理論を批判し、マネーサプライを重視してマネタリズムと呼ばれ、更に新自由主義とも呼ばれた。またロナルド・コースらは新制度派経済学や法と経済学などの分野を創始した。
マネタリスト
詳細は「マネタリスト」を参照
シカゴ学派でもあるミルトン・フリードマンが主唱。貨幣数量説の再評価などマネーサプライを重視し、ケインズ主義的な裁量的財政政策を批判して、ルールに基づいた政策の実行を提唱した。
ニュー・ケインジアン
詳細は「ニュー・ケインジアン」を参照
1990年代以降、グレゴリー・マンキューらが提唱。マネタリストや新しい古典派(ニュー・クラシカル)に対して、裁量的な財政・金融政策の有効性を提唱した。
議論
主な思想による批判
1911年の世界産業労働組合によるポスター「資本主義のピラミッド」。各層の文字は上から「資本主義」「我々はあなたを支配する」「我々はあなたを馬鹿にする」「我々はあなたを撃つ」「我々はあなたのために食べる」「我々は全員のために働く、我々は全員を養う」
詳細は「反資本主義」を参照
資本主義に対する主な思想的立場からの見解や批判には以下がある。
- 社会民主主義者らは、経済的平等など社会的公正を重視し、資本主義の枠内で修正資本主義や福祉国家などを提唱する。
- マルクス主義や社会的無政府主義などの共産主義者らは、資本主義の本質は搾取であり、私有財産制度の廃止により最終的には社会主義(共産主義)社会への移行を提唱する。
- ファシズムやナチズムは、資本主義は階級闘争を激化させ共産主義を招くとして、第三の道や第三の位置として国家や民族共同体を重視する。
- 右派リバタリアニズムは、市場経済を徹底させ、国家や政府の廃止を提唱する。
- 反グローバリズムは、グローバリズムが進展して各国政府の規制が後退し多国籍企業などの利益が優先されていると考え、地域主権、雇用確保、環境保護などの重要性を提唱する。
批判の詳細
資本主義の支持者は、資本主義は過去に作られたいかなる経済システムより優れており、その利益は主に一般の人々に与えられると主張する[28]。しかし資本主義の批判者は、多様な経済的な不安定さがあり[29]、全ての人々に幸福を提供する事はできず[30]、自然環境に持続不可能な損害を与える[31]、と論じる。
資本主義への批判には、経済システムとしての社会的不平等、不公正な富や権力の配分、物質主義、労働者や労働組合への抑圧、社会的疎外、失業、そして経済の不安定さなどが関連する[32]。多くの社会主義者は、資本主義は非合理的で、生産や経済の方向性は計画されず、多数の矛盾や内的不整合があると考えている[33][34]。資本主義と個人主義的な私有権は、所有者が賛同できないアンチコモンズの悲劇に陥っている。マルクス経済学の Richard D. Wolff は、資本主義経済では共同体の社会的必要性よりも利益と資本蓄積が優先され、資本主義企業では企業の基本的な方針に労働者を含める事は稀である、とした[35]。
労働関係の一部の歴史家や学者は、奴隷、奉公、強制された囚人などの強制労働は、資本主義における雇用関係と類似性があると論じている。Tom Brassは強制労働は資本主義に受容可能と論じた[36][37]。
資本主義の多くの側面は、主に企業による資本主義に反対する反グローバリゼーションの批判を受けている。環境主義者らは、資本主義は継続的な経済成長を必要として、必然的に地球の有限な天然資源を枯渇させ、多数の動植物を絶滅させていると論じている[38][39] 。また、新自由主義または現代の資本主義は、世界貿易を拡大する半面、伝統的な文化様式を破壊し、不平等の悪化と世界的な貧困の拡大を招いた結果、我々は新自由主義以前よりも貧困な時代に生きており、1970年以降の環境指数は大幅な環境悪化を示している、と論じている[40][41][42]。
一部の学者は2007年の金融危機の責任が新自由主義的な資本主義モデルにあると批判した[43][44][45][46][47]。
多くの宗教は、資本主義の特定の要素を批判または反対している。伝統的なユダヤ教、キリスト教、イスラム教などでは利息付きの金貸し業を禁じているが[48][49] 、銀行が設立されている。一部のキリスト教徒は資本主義を、その物質主義崇拝では全人類の幸福を測る事はできないと批判している[50]。カトリックの学者と聖職者はしばしば、貧困層を排除した分配に関して免責されていると、資本主義を批判してきた。 ローマ教皇のフランシスコは、解き放たれた資本主義は「新たな専制」として、世界の指導者に対して貧困と不平等に対する戦いを呼びかけた[51]。
脚注
- ^ Zimbalist, Sherman and Brown, Andrew, Howard J. and Stuart (October 1988). Comparing Economic Systems: A Political-Economic Approach. Harcourt College Pub. pp. 6–7. ISBN 978-0-15-512403-5.
“Pure capitalism is defined as a system wherein all of the means of
production (physical capital) are privately owned and run by the
capitalist class for a profit, while most other people are workers who
work for a salary or wage (and who do not own the capital or the
product).” - ^ Rosser, Mariana V. and J Barkley Jr. [要説明] (23 July 2003). Comparative Economics in a Transforming World Economy. MIT Press. pp. 7. ISBN 978-0-262-18234-8.
“In capitalist economies, land and produced means of production (the
capital stock) are owned by private individuals or groups of private
individuals organized as firms.” - ^ Chris Jenks. Core Sociological Dichotomies.
“Capitalism, as a mode of production, is an economic system of
manufacture and exchange which is geared toward the production and sale
of commodities within a market for profit, where the manufacture of
commodities consists of the use of the formally free labor of workers in
exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer
extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the
difference between the wages paid to the worker and the value of the
commodity produced by him/her to generate that profit.” London, England,
UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India. SAGE. P. 383. - ^ Heilbroner, Robert L. “Capitalism”. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume, eds. [要説明], The New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd ed. (Palgrave Macmillan, 2008) doi:10.1057/9780230226203.0198
- ^ Louis Hyman and Edward E. Baptist (2014). American Capitalism: A Reader. Simon & Schuster. ISBN 978-1-4767-8431-1.
- ^ Gregory and Stuart, Paul and Robert (28 February 2013). The Global Economy and its Economic Systems. South-Western College Pub. p. 41. ISBN 978-1-285-05535-0.
“Capitalism is characterized by private ownership of the factors of
production. Decision making is decentralized and rests with the owners
of the factors of production. Their decision making is coordinated by
the market, which provides the necessary information. Material
incentives are used to motivate participants.” - ^ Definition of CAPITALISM – merriam-webster
- ^ Gregory and Stuart, Paul and Robert (28 February 2013). The Global Economy and its Economic Systems. South-Western College Pub. p. 107. ISBN 978-1-285-05535-0.
“Real-world capitalist systems are mixed, some having higher shares of
public ownership than others. The mix changes when privatization or
nationalization occurs. Privatization is when property that had been
state-owned is transferred to private owners. Nationalization occurs
when privately owned property becomes publicly owned.” - ^ a b c Macmillan Dictionary of Modern Economics, 3rd Ed., 1986, p. 54.
- ^ Stilwell,
Frank. “Political Economy: the Contest of Economic Ideas.” First
Edition. Oxford University Press. Melbourne, Australia. 2002. - ^ Braudel p. 232
- ^ Harper, Douglas. “cattle”. Online Etymology Dictionary.
- ^ James Augustus Henry Murray. “Capital”. A New English Dictionary on Historical Principles. Oxford English Press. Vol. 2. p. 93.
- ^ Braudel p. 234
- ^ Braudel, Fernand. The Wheels of Commerce: Civilization and Capitalism 15th–18th Century, Harper and Row, 1979, p. 237.
- ^ a b 資本主義 – 日本大百科全書(ニッポニカ)
- ^ Werhane, P. H. (1994). “Adam Smith and His Legacy for Modern Capitalism”. The Review of Metaphysics (Philosophy Education Society) 47 (3).
- ^ Barrons Dictionary of Finance and Investment Terms, 1995; p. 74.
- ^ “Karl Marx Themes, Arguments and Ideas”, SparkNotes Philosopyhy Study Guides, Karl Marx
- ^ “About Cato”. Cato Institute • www.cato.org. 2008年11月6日閲覧。
- ^ a b [url=http://www.dsp.org.au/node/31 The contradictions of capitalism – DEMOCRATIC SOCIALIST PERSPECTIVE]
- ^ Althusser and the Renewal of Marxist Social Theory
- ^ Economic Manuscripts: Capital Vol. I – Chapter Thirty Two
- ^ (ARCHIVED CONTENT) UK Government Web Archive – The National Archives
- ^ James Fulcher, Capitalism A Very Short Introduction, “the investment of money in order to make a profit, the essential feature of capitalism”, p. 14, Oxford, 2004, ISBN 978-0-19-280218-7.
- ^ 「国民百科事典3」平凡社 p536 1961年8月30日初版発行
- ^ Cradle of capitalism
- ^ Friedman, Milton. Capitalism and Freedom. [Chicago] University of Chicago, 1962.
- ^ Krugman, Paul, Wells, Robin, Economics, Worth Publishers, New York (2006)
- ^ “Caritas in veritate paragraph 36”. 2014年10月7日閲覧。
- ^ McMurty, John (1999). The Cancer Stage of Capitalism. PLUTO PRESS. ISBN 0-7453-1347-7.
- ^ Korstanje,
M (2015). Review: Why Nations fail. The origins of Power, Prosperity
and Poverty. Journal of International and Global Studies. Volume 6,
issue 2. May 2015. (pp. 97–100.) - ^ Korstanje, M (2015). A Difficult World, examining the roots of Capitalism. New York, Nova Science.
- ^ Brander, James A. Government policy toward business. 4th ed. Mississauga, Ontario, John Wiley & Sons Canada, 2006. Print.
- ^ Frances Goldin, Debby Smith, Michael Smith (2014). Imagine: Living in a Socialist USA. Harper Perennial. ISBN 0-06-230557-3 pp. 49–50.
- ^ Cass, Towards a Comparative Political Economy of Unfree Labor (1999)
- ^ Marcel van der Linden (Fall 2003). “Labour History as the History of Multitudes”. Labour / Le Travail 52: 235–44. doi:10.2307/25149390. JSTOR 25149390. オリジナルの17 December 2007時点によるアーカイブ。 2008年2月26日閲覧。.
- ^ George Monbiot (1 October 2014). It’s time to shout stop on this war on the living world. The Guardian. Retrieved 31 October 2014.
- ^ Dawson, Ashley (2016). Extinction: A Radical History. OR Books. ISBN 978-1-944869-01-4.
- ^ The crisis of neoliberalism. The Real News. 30 March 2010. Retrieved 3 January 2014.
- “When we speak of neoliberalism, we speak of contemporary capitalism.” – Gérard Duménil, former Research Director at the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
- ^ Jones, Campbell, Martin Parker and Rene Ten Bos, For Business Ethics. (Routledge, 2005) ISBN 0-415-31135-7, p. 101.
- ^ IMF: The last generation of economic policies may have been a complete failure. Business Insider. May 2016.
- ^ Lavoie, Marc (Winter 2012–2013). “Financialization, neo-liberalism, and securitization”. Journal of Post Keynesian Economics 35 (2): 215–33. doi:10.2753/pke0160-3477350203. JSTOR 23469991.
- ^ Susan Braedley and Meg Luxton, Neoliberalism and Everyday Life (McGill-Queen’s University Press, 2010), ISBN 0-7735-3692-2, p. 3
- ^ Manfred B. Steger and Ravi K. Roy. Neoliberalism: A Very Short Introduction. (Oxford University Press, 2010.) ISBN 0-19-956051-X. p. 123.
- ^ Gérard Duménil and Dominique Lévy, The Crisis of Neoliberalism. (Harvard University Press, 2013), ISBN 0-674-07224-3
- ^ David M Kotz, The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism (Harvard University Press, 2015), ISBN 0-674-72565-4
- ^ Baba Metzia 61b
- ^ Moehlman, 1934, pp. 6–7.
- ^ “III. The Social Doctrine of the Church”. The Vatican. 2008年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月26日閲覧。
- ^ O’Leary, Naomi, “Pope Attacks ‘Tyranny’ of Markets in Manifesto for Papacy”. Reuters (November 2013). Retrieved 30 December 2013.
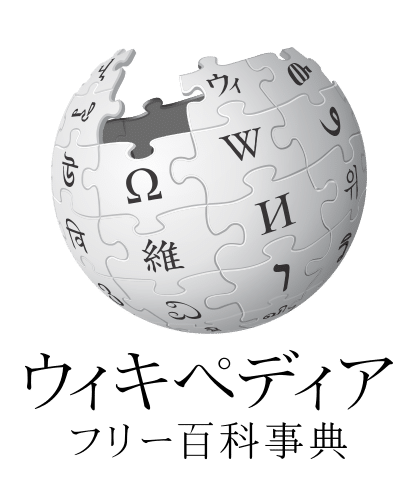
最新ニュース
coron's Source - 全国 generated by Nordot
- BookLive/「ハラカド」に推し活拠点「OSHI BASE Harajuku」オープンby 流通ニュース on 2024年4月18日 at AM 1:49
TOPPANホールディングスのグループ会社BookLiveは4月17日、東京・原宿に開業した東急プラ...
- スケボー、堀米雄斗が新所属契約 ストリートの東京五輪王者by 共同通信 on 2024年4月18日 at AM 1:46
スケートボード男子ストリートで東京五輪金メダルの堀米雄斗(25)が18日、三井住友DSアセットマネジ...
- 米オラクルが日本国内に1兆円超投資へby 共同通信 on 2024年4月18日 at AM 1:42
- イスラエル北部も交戦激化 レバノンから攻撃、兵士負傷by 共同通信 on 2024年4月18日 at AM 1:24
【エルサレム共同】イスラエル軍は17日、レバノン領からイスラエル北部に向け、対戦車ミサイルや無人機に...
- 大谷、今季3度目の3安打 盗塁も記録、吉田は出番なしby 共同通信 on 2024年4月18日 at AM 1:17
【ロサンゼルス共同】米大リーグは17日、各地で行われ、ドジャースの大谷は本拠地ロサンゼルスでのナショ...
- 高知県宿毛市内の全小中学校が臨時休校by 共同通信 on 2024年4月18日 at AM 1:17
- ライフ/3月総売上高は693億円、既存店売上高7.1%増by 流通ニュース on 2024年4月18日 at AM 1:16
ライフコーポレーション(2024年2月期:売上高8097億円)が発表した3月の月次によると、総売上高...
- アダストリア/ライフスタイルブランド展開「トゥデイズスペシャル」子会社化by 流通ニュース on 2024年4月18日 at AM 1:16
アダストリアとウェルカムは4月17日、ライフスタイルブランド「TODAY’S SPECIAL」と「G...